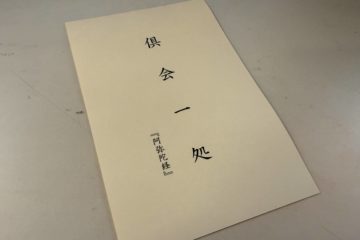鬼も悟れば仏となり 仏も迷えば鬼となる (古歌)
令和7年の節分は二月の二日。大安も重なって大変おめでたい日でした。
節分は春夏秋冬、四つの季節の変わり目の夜のことで、立春、立夏、立秋、立冬にそれぞれあります。節分といえば立春となったのは、それが一年の始まりでもあったからだと言われています。
季節の変わり目には邪気が溜まります。この邪気を払うのが追儺(ついな)の儀式で、節分の豆まきとなるわけですが、豆は鬼を払う武器であると同時に、我が身に溜まった邪気の依り代でもあるわけです。
一方「鬼は外と」と追い立てられる鬼からすれば、居場所がなくなって辛い厄日です。
鬼のイメージとしては、地獄の閻魔大王に仕える獄卒ではないかと思いますが、獄卒いわば看守であって悪者ではありません。「悪い者」「恐ろしい者」の代名詞である鬼も、本来は「強い者」の象徴であって、全国には村を守った鬼、悪霊を追い払った鬼、幸福をもたらす鬼の伝説もたくさん残っています。ですから地域によっては、豆まきで「福は内、鬼も内」とするところも少なからずあります。
臨済宗の大本山東福寺では、節分に「鬼は内、福は外」と掛け声をかけるのだそうです。
佛の教えからすると、邪気とは自分自身に他ならない。鬼とは自身自身だとなるわけです。幸福は外の人に配って、自分は中にいる鬼と対峙し、鬼を飼い慣らす事ができれば、鬼は佛にも味方にもなって、我が身を守ってくれるだろうと。
節分の今日ばかりは害となることは全部鬼のせいにして、鬼は外、福は内。
それで本当に払えればよいのですが、そうも簡単ではないはずで、これを縁日として、自らの内に潜む鬼に気付き、向き合うことができれば、その先の本来の清浄な仏心の自覚に近づくことができます。
節分は、そんな正しい生き様への再出発の日なのです。