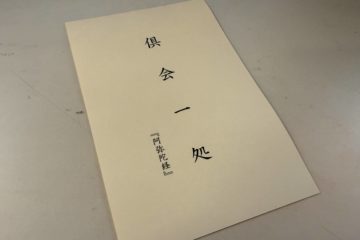過去帳の電子化を進めています。
名簿に紐付けて誰が誰のご先祖様かを検索できるようにしています。これまでは、大体いつ頃に亡くなっていたのかと、誰が喪主であったかの情報をから、当たりをつけた年の過去帳を片っ端から調べるという方法でしか調べようがありませんでした。
現時点では昭和元年頃まで入力が終了して検索ができるようになりましたが、そろそろ限界かな~と。というのも大正に入ると、過去帳で使われている漢字が現在のものでなかったり、崩し文字になったりして、古文書解読状態になります。また、過去帳は和綴じの帳面に筆で書かれており、虫食いがひどく手荒には扱えません。昭和元年頃までは先代の由木先生がコピーを取って製本した控えがあったので、それを参照していましたが、それ以前は原本しかありません。
そこで実際に解読して入力するかはさておき、進む劣化の観点からバックアップは取っておこうと、このたび明治二年以降の過去帳を全てPDFにしてみました。一ページ一ページ捲ってスキャニングしてみると、なかなか面白い事が分かります。例えば、明治5年のページには
「以来平民苗字可相用御布告」とあり、1月21日の長蔵の娘 と書かれた女性を最後に、1月26日以降は、上○五郎(一部判読できず)の孫 、のように喪主の姓名が記載されるようになります。また特に驚かされるのが、子どもの死亡の多さで、年間100人の方が亡くなるとすると、そのうち約40人は流産や死産、7歳未満の子どもで、ちゃんと成長することの素晴らしさがよく分かります。七五三がかくも盛大な理由も察せられます。
他にも明治5年4月に亡くなった、六蔵の欄には、「当山二十三代住職の念譽上人に35年間給仕として仕える。俗名は六蔵。越後の国出身で新川群南保村の九重郎の倅」との付記があります。南保村は今の富山県にある地名ですので、越後ではなく越中だろうと思いますが、どういう事情で流れてきたのだろうかと、想像が膨らみます。
使われている用紙も明治17年から罫線が印刷された用紙に変わります。それまでは無地の和紙だったのが工業製品に変わっています。
もはや解読が難しく、データ化は難しい気がしますが、とりあえずバックアップとして製本しておこうと思います。この表紙には四十三号とありますので、まだまだ遡れるはずですがまずは山内を探索するところからですので、まだまだ先は長そうです。